不動産投資による税金の対策は、ネットなどで「節税目的はNG」と語られることもあります。
しかし実際には、投資対象や税率差を正しく理解できていれば、節税対策として十分活用が可能です。
一方で「不動産投資では大きな節税効果が得られず、むしろ失敗した」というケースが出るのは、多くの場合、税率差が活かせない物件を売りつけられたり、十分にシミュレーションを行わずに購入した結果といえます。
この記事では家賃収入と税金にまつわる仕組みや、失敗を回避するための具体的なポイントを解説していきます。
目次
不動産投資で節税しやすいのは所得が高い人
不動産投資を通じて家賃収入の税金を抑える場合、もっとも効果を発揮するのは、給与所得が高く、所得税・住民税率が高い層です。
例えば、課税所得が900万円を超える人であれば、減価償却による「会計上の赤字」と給与所得を相殺して(損益通算)、大きく納税額を下げることが見込めます。
具体的には、減価償却費が多く取れる築古木造物件を選ぶことで、会計上の赤字をしっかり作り、その赤字分を給与所得とぶつけて全体の所得を圧縮する手法が有効です。
たとえば、年収1,200万円クラスの人であれば、減価償却期間中に数百万円の節税が実現できることも珍しくありません。
節税には2種類の効果がある
不動産投資による節税には、大きく分けて2つの効果がある点を押さえておきましょう。
- 実質的に税金を減らす
減価償却期間中の高い所得税・住民税率と、売却時の譲渡税率(長期譲渡の場合は20%)に差をつけることで、最終的に支払う総税額を減らせる。
例えば、課税所得1,500万円クラスで約33%の税率が掛かる人が、売却時に20%の譲渡税率で済ませれば、その差し引き分は実質的に減税効果となります。 - 税金を後ろにずらす(繰り延べ効果)
減価償却期間中は家賃収入の税金が抑えられるが、物件売却時には減価償却した分を譲渡益として計上する。
結果として、納税を後ろに送っている形になる。ただ、繰り延べであっても、そこまでの間に増えたキャッシュを再投資できるメリットがあります。
減価償却で作った赤字を損益通算し、所得を圧縮する仕組み
減価償却とは?
家賃収入から経費を引いた額が「不動産所得」だが、投資物件の場合は「減価償却費」が大きなカギになる。
減価償却費とは、建物が年々劣化すると想定して費用計上する仕組みで、実際のキャッシュアウトがない経費として扱われる。
例えば、木造築古物件を購入すると、法定耐用年数が短いことで毎年多額の減価償却ができるため、会計上の赤字(実際にはキャッシュフローが黒字でも)を作りやすい。
会計上の赤字と給与所得との損益通算
不動産投資で作った赤字は、給与所得など他の所得と相殺(損益通算)できる。つまり、家賃収入の税金を減らすどころか、本業の給与所得にかかる税金まで減らす効果が期待できるわけだ。
ただし、損益通算による節税効果が顕著に出るのは、所得税率・住民税率が高い層に限られる点が重要。
課税所得が900万円を超えてくると税率は30%超となり、売却時の譲渡税率20%(長期保有)との差が大きくなるので、結果的に支払う税金が実質的に減る。逆に年収がそこまで高くない層の場合、税率差が小さいため実益が小さい。
デットクロスに注意
減価償却期間が終わった後は、大きな経費計上ができなくなり、会計上の利益と納税額が増える「デットクロス」リスクが生じる。
書類上は黒字でも、借入返済などを考慮すると手元資金が圧迫されかねない。よって、減価償却が切れる前に売却するか、さらに別の減価償却費を生む物件を買い増しするなど、計画的な対策が必須だ。
節税に向いている人・物件と、向かない人・物件
所得が高い人・築古木造物件がベスト
- 課税所得900万円超(年収目安1,200万円超)の場合、減価償却による赤字と高い税率を相殺することで大きな節税が見込める。
- 築古木造は法定耐用年数が短く、1年あたりの減価償却費が多いため、会計上の赤字を大きく作りやすい。
- 具体的には、「木造アパートで築古、耐用年数切れを起点に法定耐用年数×20%の再設定」などの仕組みを活用すれば、節税効果が最大化しやすい。
所得が低めの人・新築区分マンションは厳しい
- 課税所得が900万円以下だと、減価償却で作った赤字を相殺しても、税率差が小さく実質節税額がさほど大きくならない。
- 新築物件は長い法定耐用年数により、年ごとの減価償却費が少ないので赤字幅が小さく、節税目的には適しにくい。
- とりわけ新築区分マンションは割高なこともあり、減価償却費以上に家賃収入が上乗せされて所得税がむしろ増えてしまう可能性もある。
三大誤解と対策
「赤字だと融資審査に不利?」
銀行は実質キャッシュフロー(減価償却前の利益)を重視する。帳簿上の赤字があってもキャッシュフローが黒字なら審査への悪影響は小さい。
「減価償却で赤字になる物件は収益性が低い?」
新築・築浅など耐用年数が長い物件を想定した論だが、築古木造は高い収益性と大きな減価償却費を両立できるケースが多い。
「結局は納税を先送りしているだけ?」
確かに、減価償却した分は売却時に譲渡益として課税されるが、高所得者は減価償却期間中の所得税率と売却時の譲渡税率(長期20%)の差によって実質的に税金を減らせる。
失敗例:節税にならない物件を買ったケース
新築区分マンションを複数購入
A氏は営業マンに勧められて新築区分をいくつも買ったが、家賃収入は少なく減価償却費も小さいため、節税効果が出なかったどころか返済で苦しくなり、さらに減価償却がほぼ終わったあとの追加融資も受けづらくなった。
新築一棟マンションでむしろ税負担増
高所得のB氏が新築マンションを買ったが、減価償却費が少なく、家賃収入がそのまま所得を押し上げる形に。
結果として給与所得+不動産所得で大幅に課税が増え「節税になる」と聞いていた話と真逆の状況に陥った。
所得税以外の節税にも効果
相続税対策
現金をそのまま持っていると相続時に評価額が高くなるが、不動産に変えておけば、賃貸物件としての評価額が下がる可能性があり、相続税を抑えられる。例えば2億円の現預金を不動産に変えれば、評価額が5~6割程度に下がるケースも。
法人税の繰り延べ効果
法人として不動産を保有する場合、減価償却によって法人税が抑えられるうえ、売却時のタイミングや赤字との相殺によって巧みに税負担を繰り延べできる。短期的には手元資金を増やし、別事業に再投資するメリットが生じる。
まとめ
不動産投資による家賃収入の税金対策は、所得税や住民税と譲渡税率の“差”を活用し、会計上の赤字を損益通算して所得を圧縮するやり方が大きな柱となる。
中でも効果を最大化しやすいのはこの2条件に該当する場合。
- 所得税・住民税率が高い(課税所得900万円超)
- 減価償却費を大きく取れる築古木造物件
逆に、新築区分マンションは法定耐用年数が長く、毎年取れる減価償却費が少ないため、期待していたほど家賃収入の税金が下がらず失敗例が多い。
また、減価償却期間が終わると税金が急増する「デットクロス」対策として、売却のタイミングや買い増し戦略をあらかじめ考えておくことが欠かせない。
最終的に、不動産投資で節税を狙うなら「自分が高所得かどうか」と「減価償却に有利な物件を買うか」が肝要である。
適切な物件選定と長期的な売却計画を立てることで、実質的に税負担を抑えながら安定したキャッシュフローを得ることができるだろう。
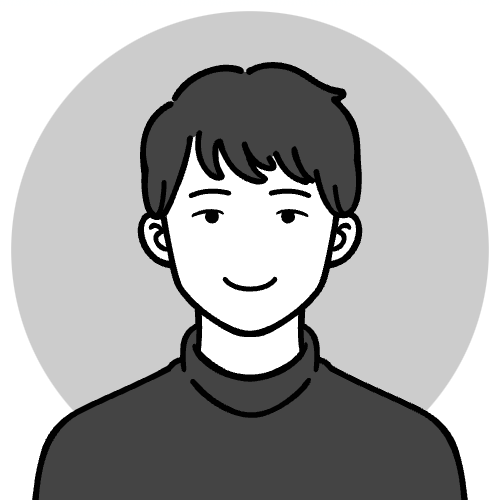
佐藤
