不動産投資を始める際、多くの方が気になるのは「どのくらいの初期費用が必要なのか」という点ではないでしょうか。
一般的に、不動産投資の初期費用は物件価格の15%前後が目安と言われています。
ただし、これはあくまでも目安であり、購入する物件の性質や融資条件、購入タイミングによって大きく上下します。
この記事では、不動産投資の初期費用の内訳や種類、初期費用を抑える方法などについて詳しく解説します。
ぜひご自身の状況と照らし合わせて、不動産投資に必要な資金計画を立てる際の参考にしてください。
目次
不動産投資の初期費用は物件価格の15%が目安
一般的に、不動産投資を始める際の初期費用は「物件価格の15%ほど」と言われます。
たとえば、3,000万円の物件なら450万円、7,000万円の物件なら1,050万円が大まかな目安です。
もちろんこれは平均的な指標であって、融資の状況や物件の種類、購入スキームなどによって変動します。
なぜ15%ほどになるかというと、物件の購入時には以下のような費用が発生するためです。
・頭金(融資の自己資金部分)
・融資関連費用(事務手数料・保証料など)
・各種税金(印紙税・登録免許税・不動産取得税など)
・仲介手数料 ・火災保険料や地震保険料
・その他、登記手続きを依頼する司法書士報酬 など
ただし、最も大きなウエイトを占めるのが「物件の頭金」です。
融資によって購入費用の何%までまかなえるか、自己資金はどの程度必要なのかといった部分によって、初期費用は大きく増減します。
たとえば、フルローンを受けられれば頭金がほぼ不要になるため、初期費用が一気に抑えられますが、物件や個人の属性によっては融資が制限され、物件価格の半分ほどを頭金で賄わなくてはいけないケースもあります。
初期費用に含まれる代表的な費用と目安
不動産投資の初期費用に含まれる代表的なコストを、具体的に確認していきましょう。以下では7,000万円程度の物件を想定した場合を例にしながら、主要な費用項目と大まかな目安を紹介します。
物件の頭金
不動産投資で物件を購入する際、自己資金として用意するのが「頭金」です。
たとえば、物件価格の90%を融資で賄える場合、残りの10%は自己資金で準備する必要があります。
7,000万円の物件を購入する場合であれば、700万円が頭金の目安です。ただし、実際の融資割合は個人の年収・資産や物件の築年数・所在地などで変動します。
融資事務手数料
銀行などの金融機関で融資を受ける場合にかかる「融資事務手数料」があります。融資金額の1%~3%が相場で、たとえば、6,300万円(7,000万円のうち90%を融資)を借りる場合、1%なら約63万円、2%なら約126万円ほどかかります。金融機関によっては一律の定額制を採用しているところもあるため、詳細は取引予定の金融機関の条件を確認しましょう。
融資保証料
金融機関の融資には、多くの場合、保証機関による保証がセットになっています。融資が返済不能になったとき、保証会社が金融機関へ弁済し、保証会社が借主に請求する仕組みです。保証料は融資額の1%前後が一般的ですが、一括払いか金利上乗せかなど支払い方法によって差があります。頭金と同様に、個人属性や物件評価などで条件は異なります。
印紙税
不動産の売買契約書や金銭消費貸借契約書(融資契約書)を取り交わす際に必要になるのが「印紙税」です。
印紙を貼って納税する形になり、契約金額に応じて税額が変わります。
7,000万円クラスの不動産売買契約では、だいたい9万円ほどです。また、融資契約書の金額も加味しなくてはいけません。
登記費用(登録免許税)
物件を購入したり抵当権を設定したりする場合、登記を行う必要があります。この際にかかるのが「登録免許税」です。
計算は「固定資産税評価額 × 税率」で行われるため、評価額や建物の用途によって変わります。
7,000万円クラスの物件の場合、登録免許税は数十万円程度が目安です。
司法書士報酬
登記やその他の法的手続きは、司法書士などの専門家に依頼するのが通常です。
これらの業務依頼にかかる報酬は10~15万円ほどが一般的。物件価格が高額になるほど費用が増える場合もあるため、詳細は見積もりを取っておくと安心です。
仲介手数料
不動産会社が売主でない限り、物件探しから契約まで仲介をしてもらった場合は「仲介手数料」がかかります。
法律上の上限額は「物件価格の3% + 6万円(税別)」で、7,000万円ならおよそ216万円(税別)ほどです。ただし、仲介手数料を安く設定している業者も一部存在するため、業者選びで差がつきます。
不動産取得税
不動産を取得したときに課される「不動産取得税」は、取得した翌年以降に通知書が届き、納税するのが一般的です。
税額は「固定資産税評価額 × 税率」で算定されますが、住宅や土地には軽減措置が適用される場合が多いため、実際の負担額はもう少し下がります。
築年数や建物の規模などにも左右されるため、購入予定の物件ごとにシミュレーションが大切です。
固定資産税・都市計画税の精算
毎年1月1日時点の所有者に課税される固定資産税と都市計画税は、売買のタイミングで売主と買主の間で精算を行う習慣があります。
引き渡し日以降分の税金を買主が負担する形をとることが一般的です。
金額は物件の構造やエリアによって異なりますが、固定資産税評価額でおよそ数十万円程度です。
火災保険料・地震保険料
物件を融資利用で購入する場合、金融機関から火災保険・地震保険への加入を義務付けられるケースがあります。保険料は物件の構造や築年数、補償期間・補償内容によって大きく変わります。たとえば木造と鉄筋コンクリート造で火災保険料は大きく異なるため、保険会社やプラン選びが重要です。
初期費用を抑える3つの方法
ここまで見てきたように、物件価格の15%ほどが初期費用の目安になりますが、工夫次第である程度抑えることが可能です。ここでは代表的な3つの方法を紹介します。
売主が不動産会社の物件を選ぶ
仲介手数料は大きな比重を占める費用のひとつですが、不動産会社が売主の場合は仲介が入らないため、仲介手数料が発生しません。物件価格が大きいほど手数料は高額になるので、仲介手数料が0円になるメリットは非常に大きいといえます。
土地値物件を狙う
土地値物件とは、土地の価格と購入金額が近い、すなわち実質的には「土地を買っているようなもの」に近い価格設定の物件です。
融資評価が高くなりやすいことから、フルローンに近い融資を受けやすいというメリットがあります。
頭金を大幅に減らせる可能性があるため、初期費用を抑えたい人はチェックしてみると良いでしょう。
融資アレンジに強い業者に依頼する
融資を活用した不動産投資では、どの金融機関と取引するか、そしてどのような融資条件を引き出せるかが重要になります。不
動産会社によっては融資アレンジに強みを持ち、多数の金融機関とのパイプを持つケースもあります。
こうした業者だと物件価格全額に近い融資をアレンジできる可能性があり、頭金の負担を最小限に抑えられるかもしれません。
運用段階でも追加費用がかかる点に注意
物件を購入した後は「家賃収入」が入るようになり、いわゆる不労所得のような形で利益を得られますが、運用段階でもいくつかの費用が発生します。代表的なものとしては下記が挙げられます。
・固定資産税
・都市計画税
・修繕費用
・空室が出た際のリフォーム、クリーニング代(原状回復)
・広告費(空室を埋めるための費用)
・管理委託料
たとえば築古物件だと、屋根や外壁、配管などの大規模修繕費が思わぬタイミングで必要になるリスクがあります。
また、入居者退去時にリフォームを行うための資金が確保できていないと、募集ができず空室が長期化するかもしれません。
そのため、初期費用をまかなうだけの資金があったとしても、ある程度の運転資金を別途確保しておくのが現実的です。
まとめ
不動産投資の初期費用は、一般的に物件価格の15%ほどが目安とされています。
大きなウェイトを占めるのは「頭金」であり、融資条件によって自己資金額は大きく変動します。融資関連費用や税金、仲介手数料、火災保険料などさまざまなコストも加わる点をふまえると、あらかじめしっかりと資金計画を立てることが大切です。
初期費用を抑えるには、
・売主が不動産会社で仲介手数料がかからない物件を探す
・土地値物件を狙いフルローンを引き出す
・融資アレンジに強い業者に依頼して頭金を減らす といった工夫が効果的。
また、物件購入後にも修繕費や広告費など運用時の支出が発生するため、初期費用だけでなく運転資金の確保を検討しておきましょう。
不動産投資はまとまった初期費用が必要な分、成功すれば家賃収入が定期的に入る魅力的な投資手法です。
ぜひこの記事を参考にして、初期費用と運用時のコストを把握しながら、失敗を回避できる堅実な不動産投資を目指してください。
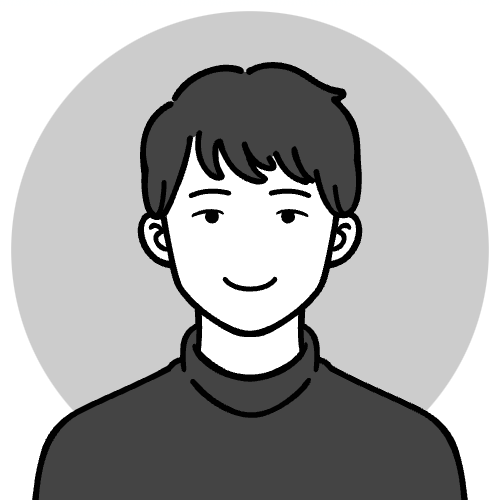
佐藤

